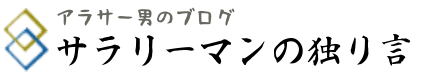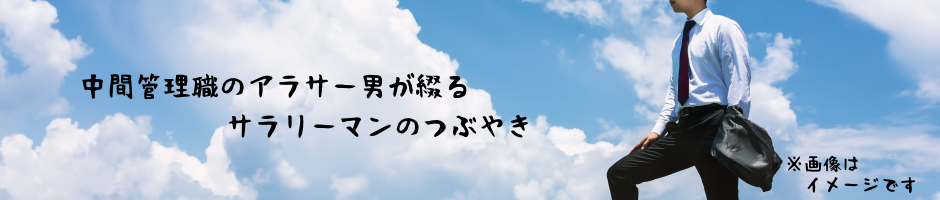専門職制度とは
サラリーマンは一般職、管理職などの分類があり、基本的には一般職からスタートするものの、業種によってはエンジニアからのスタートもあります。
その場合、ある程度の年齢になると管理職になるか否かの決断を迫られ、これまでは多くのエンジニアが専門的な仕事を退いて管理職になってきました。
しかしながら、技術によってはその人材を管理職にしてしまうことによって会社としては大きな損失も招くことから、専門職と呼ばれる分類が生まれました。
エンジニアとしておこなってきた仕事をさらに追求していくことができるようになったのです。
専門職制度を導入する企業
このような立ち位置の仕事は大企業など人材の多い企業においては近年、多くの会社が導入しています。
厚生労働省のデータによれば従業員数が5000名以上の会社の場合にはおよそ半数の会社が専門職制度を導入しているようです。
しかも、1000人以上5000名未満の場合には43パーセント、300人以上1000人未満の場合には37パーセント、300人未満の場合には23パーセントなどとなっており、会社の規模が小さくなるに従って少なくなっているようです。
そうは言っても、企業規模の小さな会社の場合には、そもそもエンジニアがそのまま専門的な業務を引き続き行うことができるケースが多い傾向にありますので、小さな会社で専門職の導入が遅れているというよりもこれまで管理職主義だった大企業が専門職制度を多く導入するようになったという考え方をしてもいいのかもしれません。
給与の違いとは
ただし、同じく厚生労働省のデータによれば専門職と管理職では管理職の方が給与が高いようです。
全体の中で管理職のほうが給与が高いと答えた企業が45パーセントとなっていますので、いまも管理職のほうが待遇は良いようです。
しかし、全体の13パーセントは専門職のほうが高いと回答し、両者が同額程度と回答した企業も31パーセントですから、管理職ばかりが尊重される世の中は少しずつ変わってきているのかもしれません。
さらに今後についても同データによれば専門職制度を今後も維持していきたいと考えている企業が約3割に上るなど、企業にとって専門職制度は徐々に根付いているようです。
そのため、かつてであれば当たり前に管理職になるしかなかったエンジニアにとって、サラリーマン人生の後半の生き方は変わってきていると言えるのではないでしょうか。
これまでのように無理してまで管理職にならなくてもいいわけですから、このような多様性のある生き方ができるようになっていることはサラリーマンであればぜひとも覚えておきたいものです。
技術を持っている人間がその技術を定年まで使い続けることができるような時代になっているわけですから、この点は見逃せません。